こんにちは。2024年春募集でJICA青年海外協力隊に応募し、理科教育職種で合格・東ティモールに派遣予定の者です。
この記事では、私が実際に体験したZoomでの人物面接・技術面接の様子を中心に、聞かれた内容や当日の流れ、準備しておいて良かったことなどを詳しくお伝えします。
書類選考や選考全体についてはこちらから↓


面接はJICAから「指定された日」に実施される
書類選考に合格した後、次は人物面接と技術面接。この2つは同じ日にオンライン(Zoom)で実施されました。
注意点は、面接日はJICAから指定され、基本的に変更不可ということ。
実は私、面接日が海外旅行の当日朝に重なってしまい、スーツケースを横に置きながら受けるという、かなり慌ただしい状況でした(笑)。でも、面接が1日でも後ろにずれていたら完全にアウトだったので、ある意味運が良かったな、と思います。
Zoom面接当日の流れ
面接は全てオンラインで行われましたが、実際の流れは以下の通りでした。
- JICAから事前に送られてくるリンクにアクセス
- 受付室に入り、順番を待つ(5〜10分)
- 人物面接(15分程度)
- 昼ごはん
- 技術面接(15分程度)
自宅の静かな部屋で受けましたが、通信環境や背景、マイクのテストなどは前日にしっかり確認しておくことをおすすめします。
面接枠は20分取られていましたが、実際は15分+予備という感じでした。
人物面接:自分の思いを素直に伝える場
人物面接では、JICA職員と思われる2名の面接官とお話ししました。雰囲気はとても穏やかで、圧迫感は全くなし。
聞かれたことは主に以下のような内容でした:
- 志望動機
- どうして民間ではなくJICAなのか?親の理解は得ている?
- なんで発展途上国なのか?
- コミュニケーション力とは何だと思う?自分はできていると思う?
- フランス留学で困難だったことは?どう乗り越えた?
- 帰国後の進路はどういった気持ちでこの考えに至ったのか?
- 合格してから今までにやったことはあるか?
ほとんど書類選考の内容と同じです。
記載した内容を自分の言葉で話せるよう、友達や家族に話してブラッシュアップさせていたし、自分でも何度も考えていたことなので、何も困ることなくありのままを話せました。
合格してから今までにやったこと、に関しては、理科教育のOVのブログを読んで理解を深めていたことを伝えました。
(正直理科教師なんて教育実習でしかちゃんとやっていなくて不安があったので、どんな実験が現地でもできるのかをメインに学んでいました。)
最後には、逆質問あるいは意気込みを話していい時間をもらえたので、やる気があること、新しい挑戦ができることにワクワクしていることを伝えました。
技術面接:専門知識というより“考え方”を問われる
人物面接の後は、職種別の技術面接。
理科教育は教員経験がないといけないものが多かったこともあり、数少ない要請を読み込んで、それぞれの依頼事項に沿って、自分ができそうなことを考えてまとめていました。
Zoomの画面越しに、教員の方が1名と事務局の方が1名の計2名が参加しました。
はじめに、事務局の方から応募内容の確認がありました。
個人情報の他に、追加で聞かれたことは2つです。
① 現職参加の有無
② 他の要請で気になるものはあったか
③ ホームステイかワンルームか希望はあるか
どちらも自分から話したかったことでもあり、聞いてもらえてうれしかったです。
現職参加のつもりであることと、理科教育だと2つの要請が気になっていることを伝えられてよかったです。
また、個人的にはホームステイの方が言語習得や馴染むという観点からも有難いことを伝えました。
技術面接で聞かれたのは、以下のような内容です。
- なんで理科教育を選んだのか
- 教育現場での指導経験(あれば)
→教育実習のみ。実習の時の実験は物質の状態変化について教えた。 - 理科室を整えたりすることも必要だが知識はあるか
→化学系は一通りある。そのほかの分野は不安は残るが、知識をつけてから要請に挑む - 言葉が通じないときどうするか
→理科の実験は言葉が通じなくてもジェスチャーで伝えられたりすることろがいいところ
興味を持てるような実験をOVから学んだりしてたくさん考えていきたい
ただもちろん言語が通じた方が良いので、日常生活では自分から積極的に現地語で話すつもり
ホームステイが良いのも同じ理由
例えば、楽しそうだと思った理科の実験は、炎色反応の実験。
現地で得られるもので材料を用意して実験しているOVがいたので、自分もやってみたい
(この後こういうのもいいよって、アドバイスももらえました) - 何を子供たちに伝えたいか
→理科の楽しさ。日常生活と密接にかかわっていること。
「理科の知識をどれだけ持っているか」よりも、“理科教育に対する考え方” “現地にあるもの”をどう活かすか、工夫や考え方を重視している印象でした。
現教員の方と、教育について話せたのは楽しい時間でした。
面接を終えて感じたこと
全体を通して感じたのは、Zoomであっても“人柄”や“熱意”はしっかり伝わるということ。
私は理科教育の実務経験が豊富というわけではありませんが、面接では「現地の教育環境でどんな支援ができそうか」「自分なりにどんな工夫ができるか」という視点で話すことを意識しました。
面接官の方々も、あくまで「一緒に考えてくれる人かどうか」を見ていたように思います。
面接準備のポイント
面接前に準備しておいて良かったと感じたことは以下の2つです:
- 要請内容の読み込みとメモ作成
→どの要請が自分に合っているかを分析 - 話す練習
→回答が長くなりすぎないよう意識。実際に誰かに対して話すとよりよい。
頭で考えるだけではなく、実際に話すことは本当に大切だと感じました。自分の考えがまとまるし、新しい観点からのアドバイスがもらえます。自分から積極的に話すようにはしていましたが、それに加えて、周りに興味をもって質問をしてくれる友人・家族が多かったことは幸運でした。
最後に
面接は緊張するものですが、どちらの面接も一方的に評価されるというより、対話のような雰囲気でした。
そして何より、「自分の言葉で、自分の気持ちを話すこと」が一番大切だと実感しました。
次回の記事では、現職参加の許可をもらうまでについて綴る予定です。これから受験する方や、協力隊に興味がある方の参考になれば嬉しいです。
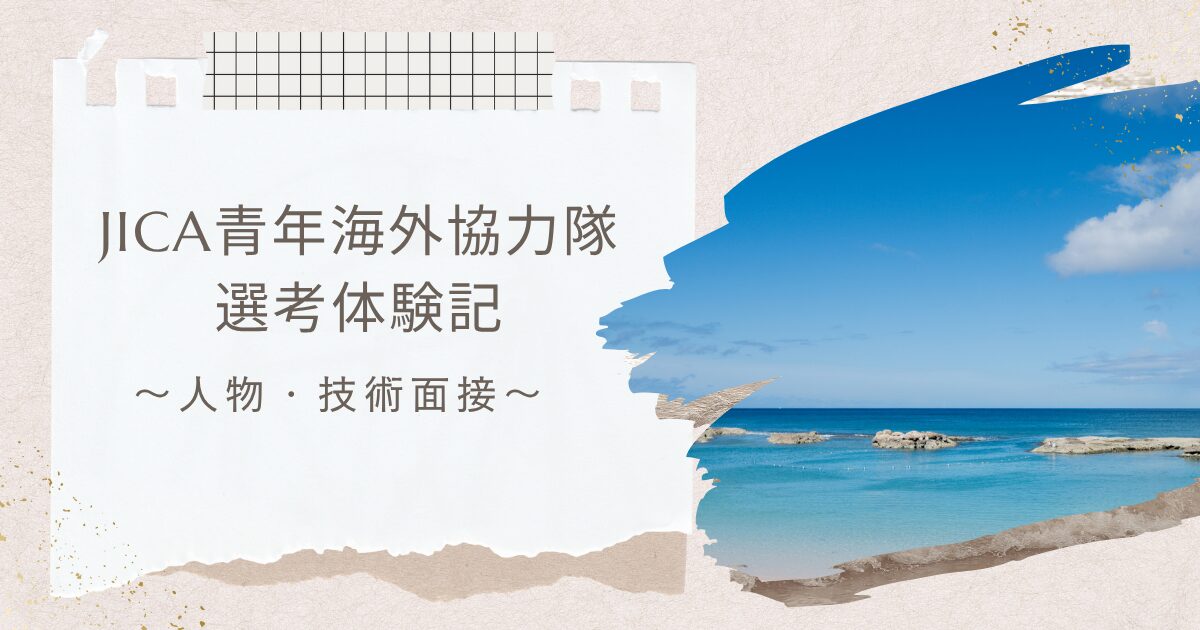



コメント